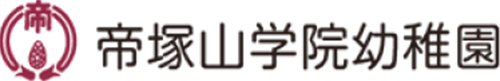今日3月3日は 桃の節句 「ひなまつり」ですね。
幼稚園でも、白酒のかわりにカルピスをいただいてひなまつりを行いました。
ひなまつり、雛人形の由来って皆さんご存知ですか?なんとなく・・・。かもしれませんね。 今日は子ども達にも、分かりやすお話をしましたよ。
皆様にはちょっと詳しくご説明しましょう。
昔、季節の節目に身の汚れを払う行事として「節句」がありました。節句には「七草がゆ」「桃の節句」「端午の節句」「七夕」「菊の節句」 の五つがあります。
その「桃の節句」がひなまつりになったんですね。
そして、雛人形は昔はなかなか子どもが育たなかったため、命を持っていかれないように、枕元に身代り人形(ひとがた)を置く風習がありました。そして、その災いを引き受けてくれた人形を流す「流し雛」へと発展し、今も受け継がれています。
また、雛人形の「ひな」(ひいな)とは小さくてかわいい物という意味があります。平安時代宮中では「ひいな遊び」(紙の着せ替え人形が盛んだったそうです。
現在のような、豪華な段飾りが飾られるようになったのは、江戸時代中期の頃だそうですよ。
今夜は、「どうぞ無事に育ちますように」「災いを引き受けて下さい」の願いを込めて ひなまつりをおこなって下さい。