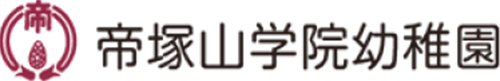本日9月12日は「十五夜」 お月見です。
幼稚園では、明後日の園庭解放で実施するお月見団子(みたらし団子)の試作を作っていると、周囲にいた子どもたちに見つかってしまい、 手伝ってもらうことになりました。
ところでお月見の由来はご存知ですか?
お月見は中国から伝来した行事であり、「中秋節」が起源とされています。中国ではこの日に月餅を食べていました。日本では奈良時代から平安時代初期頃に伝わってきて、江戸時代に庶民の間に定着しました。
もともとは、初秋(旧暦7月)、中秋(旧暦8月)、晩秋(旧暦9月)
の満月を楽しむ風習で、旧暦8月15日(現在の9月中旬)の夜を「十五夜」といい、十五夜のお月見は「中秋の名月」と呼ばれ、特に美しいとされています。この時期は、日本では農作物の収穫期でもあることから、田畑でとれたものを供えて感謝する大切な行事でもありました。特に里芋は最盛期で、皮付きのままふかした“きぬかつぎ”を供える習わしがあり、この夜の月を「芋名月」とも言うそうです。
皆さんも お月見を楽しんでみてはいかがでしょうか?